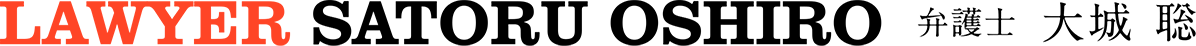制度開始から6年になる裁判員制度について産経新聞から取材を受けました。
守秘義務が壁になって、裁判員の経験が共有できていないことが、大きな問題だと思っています。
◇裁判員裁判6年、まだ足らない「社会の支援」と「経験の共有」◇
(産経ニュース)
5月で制度開始から6年を迎える裁判員制度。裁判員らが出した判決を高裁の控訴審が棄却するなど、一部議論となっているケースもあるが、関係者は「国民に制度として定着した」と評価する。その一方で、最高裁が平成21年の制度施行以来、毎年度行っている国民アンケートでは、「裁判所や司法が身近になった」と制度を肯定的に捉える割合が22年度を頂点に後退を続けるという現象も起きている。果たして国民への浸透は行き届いているのか、それとも制度の停滞なのか。識者からは「裁判員の経験を未経験者が共有する仕組みを作る必要がある」との声も上がっている。
■肯定的意見、22年度が頂点、否定は増加傾向
最高裁が裁判員制度施行後、毎年度行っているアンケート。全国の20歳以上の男女2千人前後が対象だ。項目は多岐にわたるが、その中でも制度浸透の指標となり得る複数の質問に対する回答の傾向が、関係者の頭を悩ませている。
まずは、「制度導入後、裁判所や司法が身近になった」とする設問から見てみる。最新の26年度調査では、肯定的に答えている「そう思う」が14・6%、「ややそう思う」が36・8%で合計すると約半数。「あまりそう思わない」11・5%、「そう思わない」4・0%との否定的な意見を大幅に上回っており、一見、制度の浸透が図られているようにも見える。
だが各年度を比較すると違った側面が見える。初めての調査となった21年度では、「そう思う」が22・0%、「ややそう思う」が42・0%で計6割を超える。22年度は「そう思う」24・6%、「ややそう思う」43・0%とさらに割合は上がった。しかし、22年度を頂点に肯定的意見は減少を続けており、26年度調査は過去最低となった。「そう思わない」「あまりそう思わない」とする否定的意見は、21年度の8・3%に比べて26年度は15・5%まで増加した。
■ほかの設問も傾向重なる
同様の傾向は「裁判の結果がより納得できるものになった」「裁判の結果に国民の感覚が反映されやすくなった」という設問にも当てはまる。やはり、肯定的な意見は2年目の22年度がピークで、現在は減少傾向にある。一方で否定的意見は増加傾向だ。
最高裁など司法当局では、これらの結果に対する評価は分かれているという。
あるベテラン刑事裁判官は、21、22年度の高い数値について「導入1、2年目は制度に対する期待感が大きく、さまざまなところで現在よりも多くの報道がなされた。そのため、国民の関心も高く、アンケート結果に表れた」と指摘する。
その一方で、現在の後退傾向を「制度が国民に浸透し、報道も減少したことである種の新鮮さが無くなり、高く評価する回答が後退しているのではないか」とする。ただ、「制度への批判が反映されている可能性がある」との声も根強く、アンケートへの結果は定まっていない。
ベテラン刑事裁判官は「アンケート結果を制度定着と捉えるとしても、次年度調査以降も後退傾向がさらに進むのであれば問題。国民への理解のため、広報活動を考えていく必要があるだろう」としている。
■短期は大丈夫でも「長期は負担」
国民参加の制度を浸透させるのに必要なのが、参加のハードルをいかに下げていくかだ。裁判員に仕事を休むなど大きな負担を強いる制度のため、拘束期間は常に課題となってきた。
例えば、4月に東京地裁で判決が言い渡された元オウム真理教信者の高橋克也被告(57)の裁判員裁判で、裁判員は1月上旬の選任から4カ月近く、従事したことになる。
3月に別の裁判で裁判員を務めた50代の女性は「自分の場合は選任されてから1週間で判決まで終わったので、負担は少なかった。ただ、高橋被告の裁判のような長期間の審理が可能かと言われれば、かなり難しい」と話す。
裁判員への負担が増す長期間審理になりやすい典型的な例は、高橋被告の事件のように、複数の事件で起訴されている場合だ。実は、このような場合に負担を軽減すべく、裁判員制度と同時に導入された制度がある。それは「区分審理」だ。
区分審理は事件ごとに異なる裁判員を選んで、それぞれの裁判員が事件ごとに有罪か無罪かを判断。最後の事件を審理する裁判員はその事件の有罪・無罪を判断するとともに、全事件で1つでも有罪があれば、量刑を決めなければならない。
■軽減難しく「耐えてもらうしか」
ただ、運用には常に難しさが伴ってきた。最後の事件を審理する裁判員が、直接審理に加わらなかった事件も踏まえて、最終的に判決を決めなければならなくなる。直接関わっていない事件に裁判員が適切な判断を下せるのか、導入当初から疑問の声が出ていた。
こうした意見を反映するように、区分審理を採用した裁判員裁判は、23年度の20件を頂点に減少傾向で、26年度は9件まで減っている。ある裁判官は「別事件で複数起訴された事件とはいえ、当事者や証拠が重なり、『一連の事件』として捉えなければ、判断を下せない場合が多い。そうしたケースで区分審理を行うことは適当ではない」と運用減少の背景を解説する。
長期間拘束の軽減をめぐっては、政府が3月、裁判員対象事件について「初公判から判決まで長期間にわたると見込まれる場合、裁判官だけで審理できる」ようにする裁判員法改正法を閣議決定した。ただ、この場合の長期は1年を超える裁判が対象になるとみられており、国民参加のハードルを下げるとは言い難い。
ベテラン刑事裁判官は「これまでも数カ月にわたる審理が複数あったが、選任された裁判員が次々に参加できなくなり、裁判を進行できなくなったケースは今まで出ていない。大きな負担だが、選ばれた国民の方に頑張ってもらうしかない」としている。さらに「裁判官や検察官、弁護士が論点を分かりやすく整理するなど、期間短縮に向けた努力をしていくべきだろう」とみる。
■経験共有の機会増やせ
裁判員制度に関する情報発信を行う「裁判員ネット」代表理事の大城聡弁護士は、「裁判員経験者が経験を語る場が少ないのが、アンケート結果に表れているのではないか。守秘義務を意識する余り、経験者が勤務先や家庭など社会の中で経験を語ることに抵抗感があり、何が行われているかを共有する機会がほとんどない」と指摘する。また、裁判員経験者の周辺にいる未経験者も、守秘義務が壁になり内容を聞くことを避ける傾向にあるという。
大城弁護士は、「制度開始以来、5万人以上が裁判員を経験しながら、内容を社会に還元することができていない。そのせいで、未経験者にとっては、裁判員が何をしているのか不明な点が多く、制度との距離を感じる要因になっているのではないか。経験を社会で共有する仕組みが必要だ」とみている。
また、長期審理に対する負担についても、「区分審理は問題点が多く、限られた事件でしか採用できないだろう。裁判所が審理の短期化を努力するのはもちろんだが、長期審理に参加する裁判員を社会的にバックアップすることが必要だ。そのためには勤務先や家族の理解が重要で、やはり経験の共有はカギになる」としている。